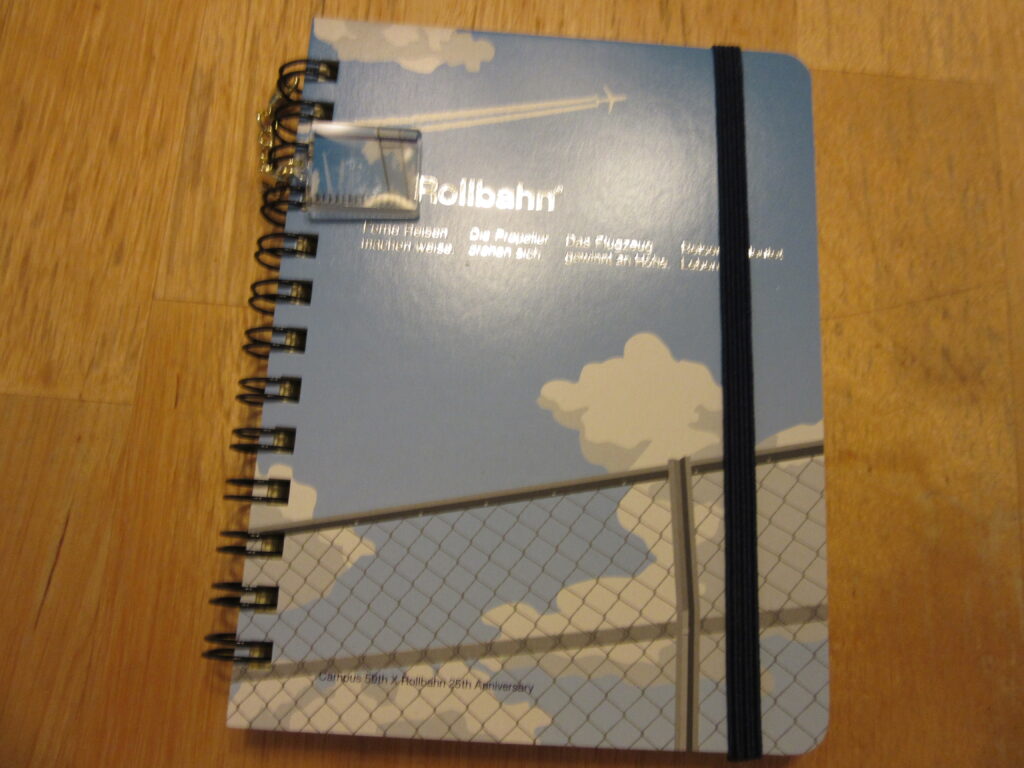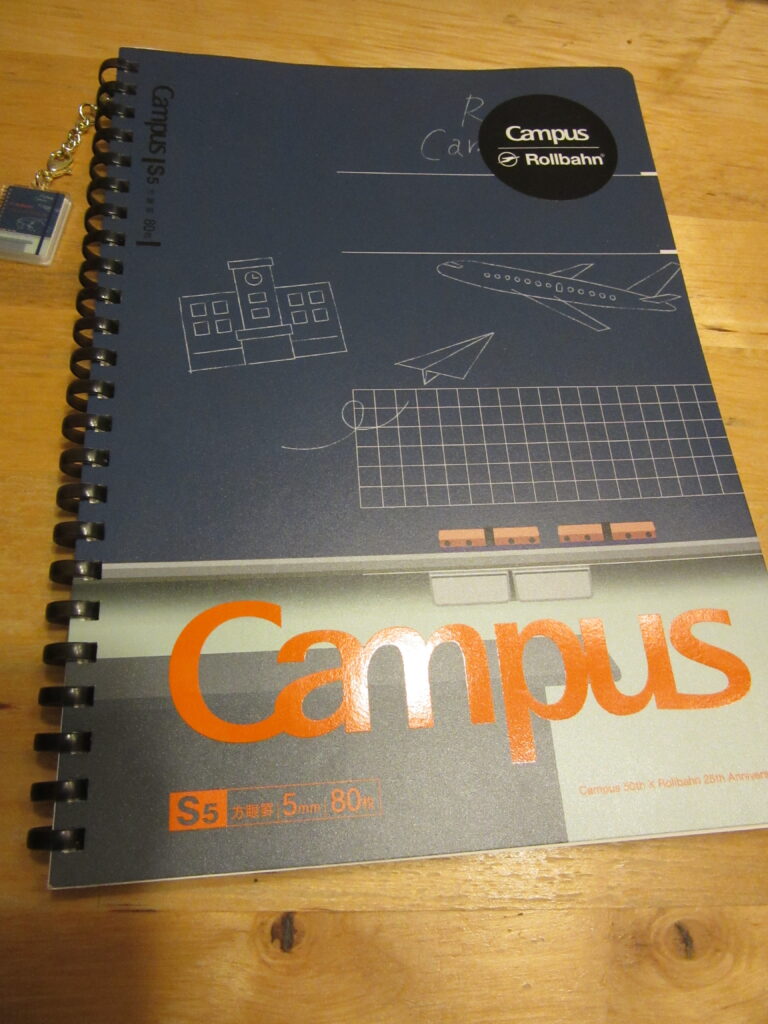みなさん、こんにちは。
先日ペットショップを訪れた際に、子犬たちが戯れている姿に
ハートを射抜かれました。
ロボットペットも気になるけど、やっぱり本物には勝てないか。
でも、生き物のお世話は大変。
うちにもまだ手のかかる子どもがいるし、これ以上時間もお金も
かけることはできない。
先日上の子が帰ってきた時に感じたのは、ああ、こういう風に育ったのかと。
それは、どんな花が育つかわからないまま種を蒔き、水や肥料を与え
日光という愛情を注ぎ、そしてこんな花が咲いたのかと。
子育ては苦労の連続でしたが、こうして花が開くと、育てるって
実は面白いことなのだと、初めて気が付きました。
下の子は、どんな花を咲かせるのだろうか?
できることなら、もっとたくさんの子どもを育ててみたかったな。
ふと、父が家庭菜園が楽しいという話をしていたのを思い出しました。
何が楽しいのか、その時はわかりませんでしたが、子育てを終えた両親にとって
育てるという楽しみは植物も変わらないのだと。
今、我が家にはクローバーが育っているのですが、もう一つお迎えしてみようか。
ということで、どうせなら四季の移り変わりを楽しめる盆栽を始めることに
しました。
「紅葉」を。
届いた紅葉は、まだ葉を落とした状態なのですが、以前もこのブログで書いたように
私は冬の枝をむき出した木も自然の造形の美しさを感じます。
なんて美しい佇まいなんだろう。
大切に育てよう。
剪定も覚えないと。
説明書を読んでも、よくわからないな。
動画を探すかな。
それでは、また。