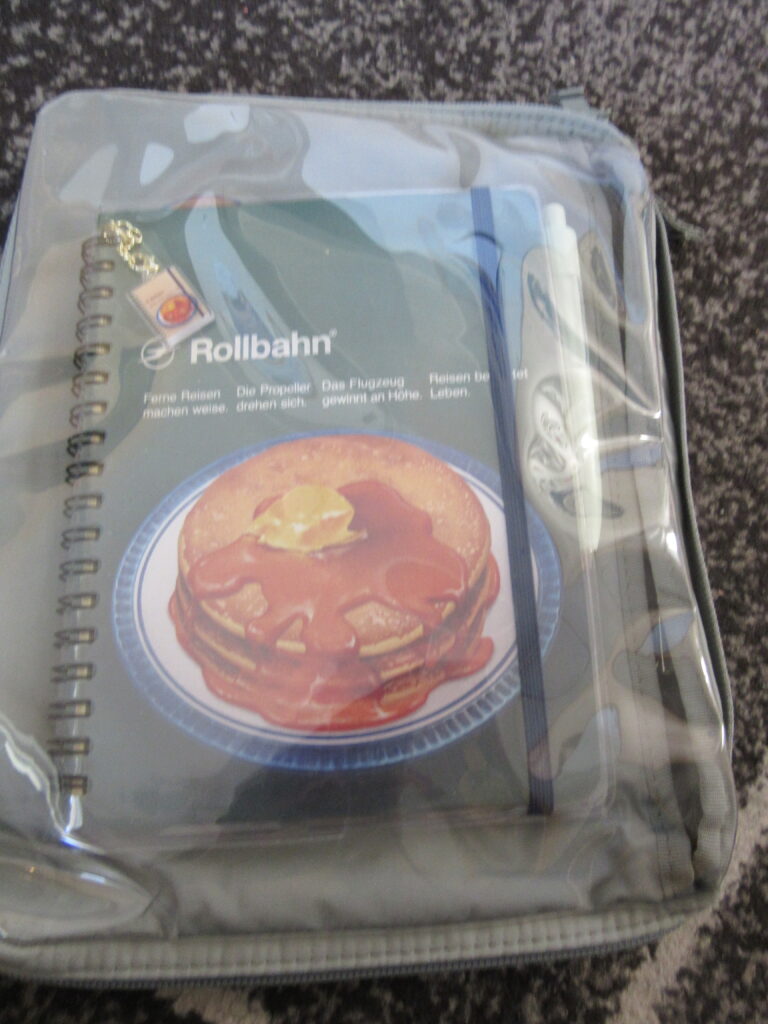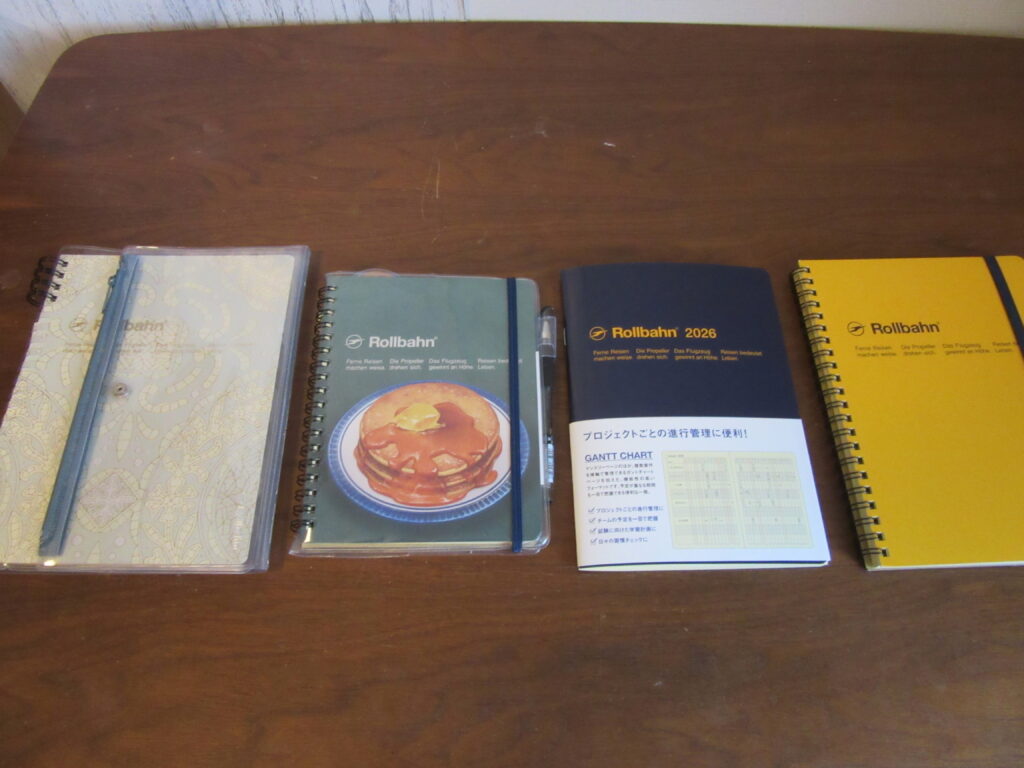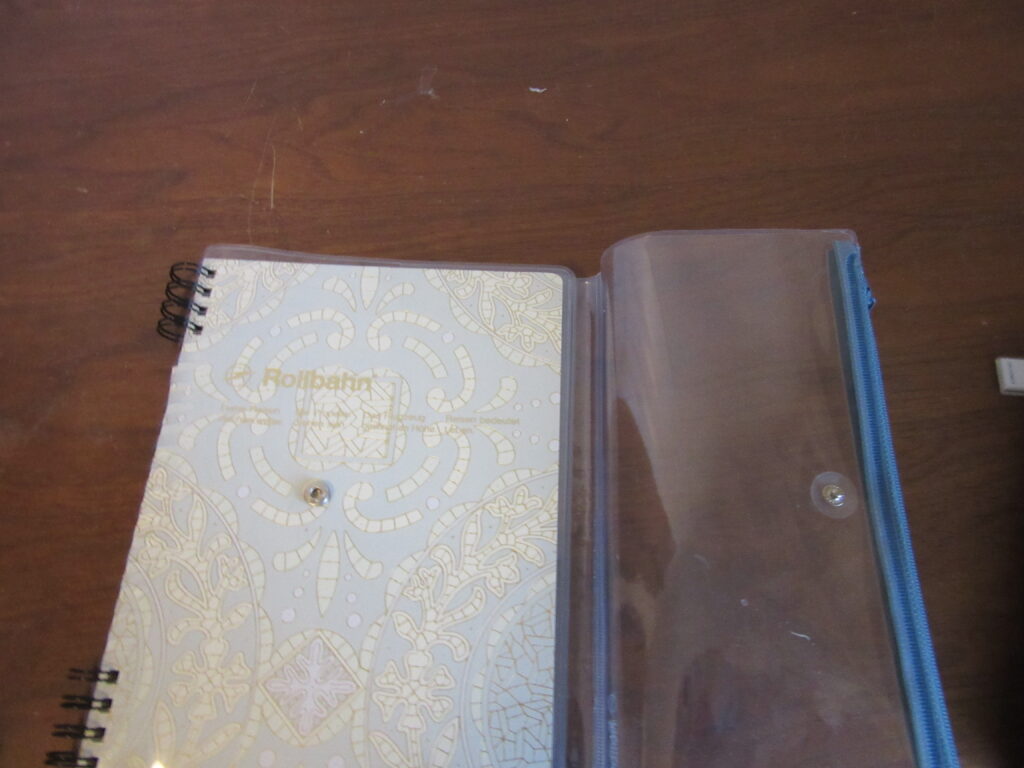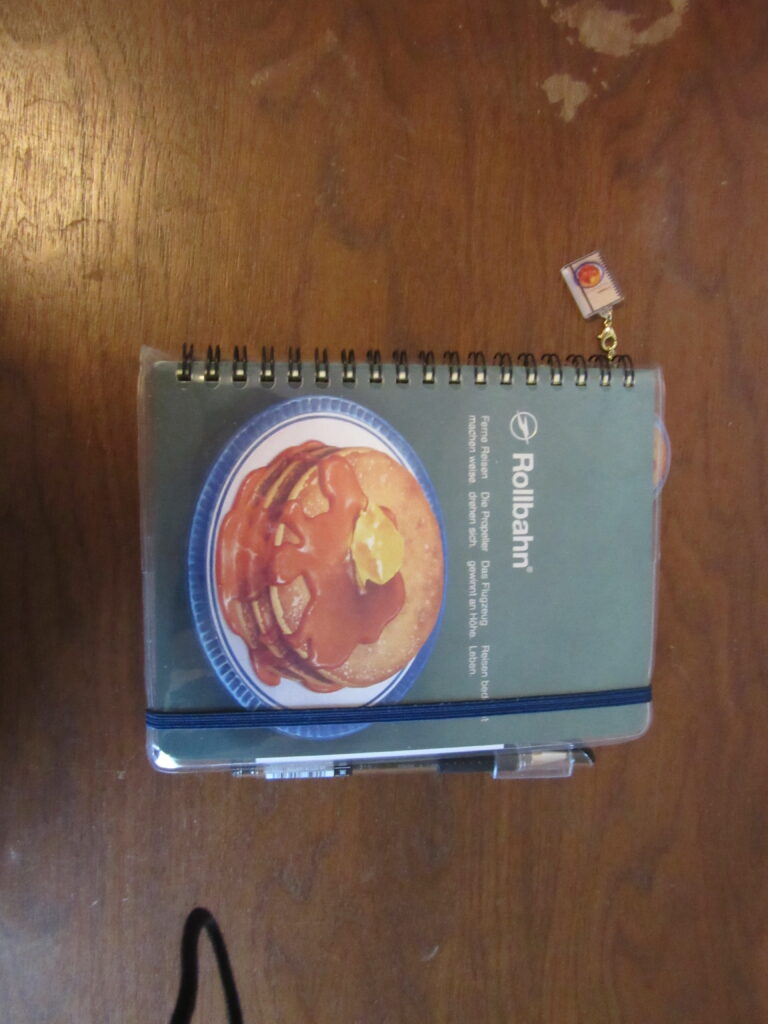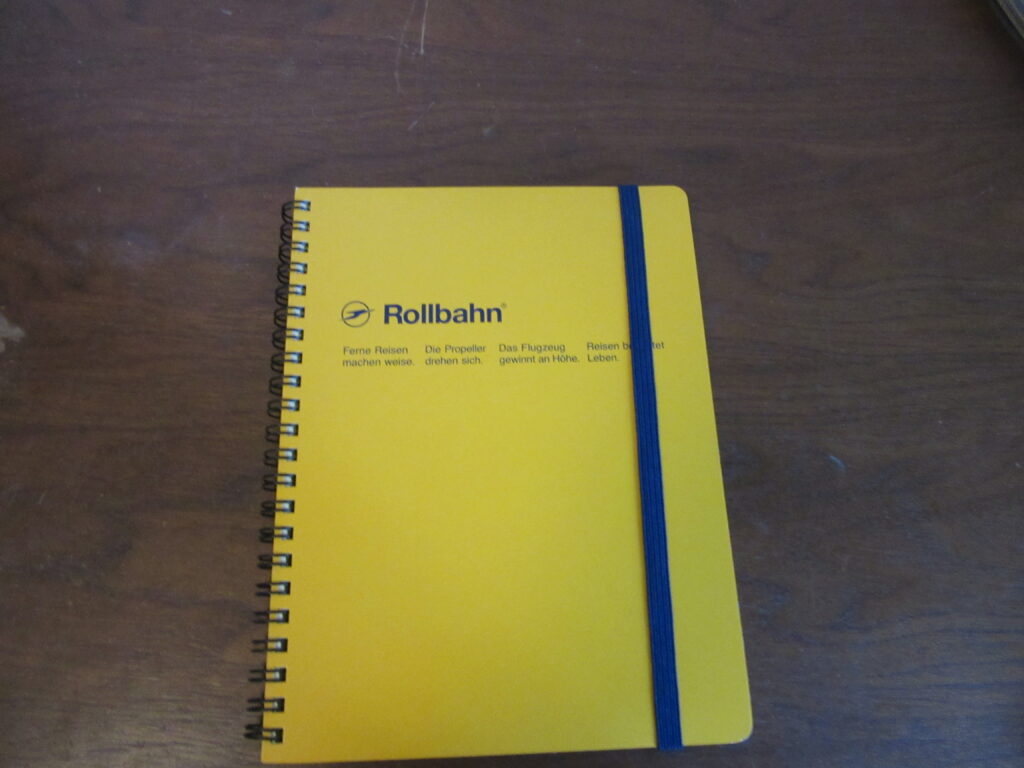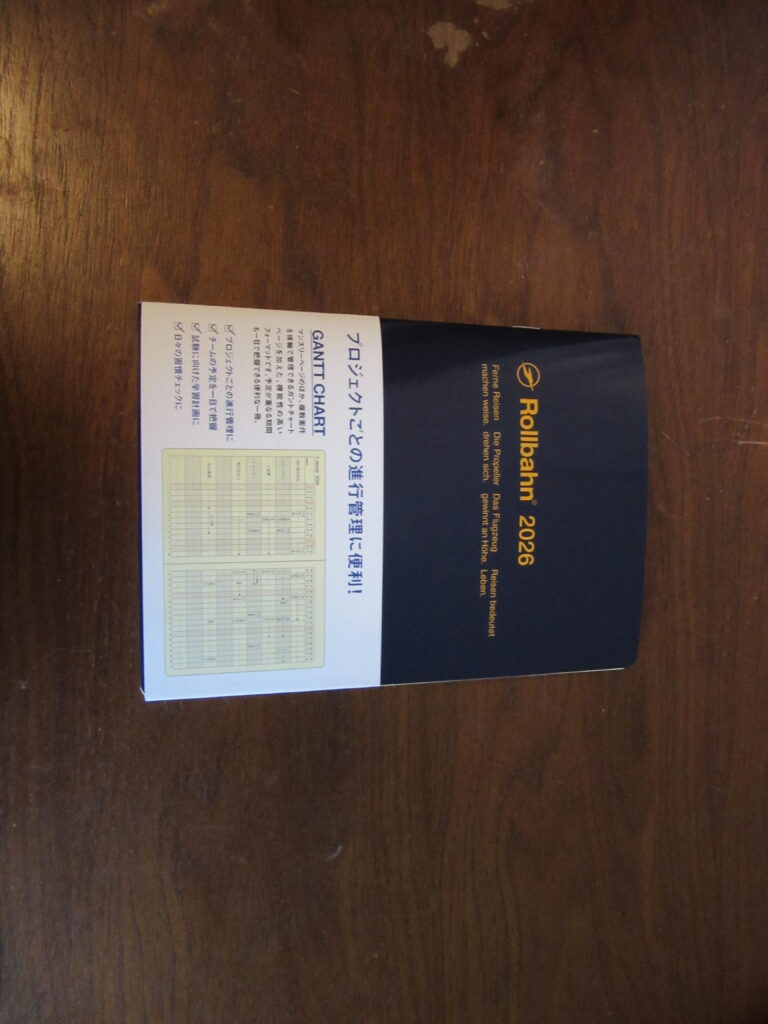みなさん、こんにちは。
師走ですが、みなさんはいかがお過ごしですか?
昨日の投稿の後、相方に来年こそは滋賀に行きたいとお願いしたところ、
行こう!今日!
と。
滋賀には訪れたいところが沢山あるのですが、広範囲に点在しているので
今回は一番行きたい場所に行くことにしました。
行きの電車の中で、その人物にまつわる本を読み、すでに胸が熱くなっておりました。
どこに訪れたのか、みなさんも気になることと思いますが、
大変残念ながら行き先をお伝えすることができません。
そこは、本当に美しく清らかで神聖な場所でした。
本当に必要としている方が、探し求めてたどり着ける場所のように感じました。
観光客でにぎわう場所ではなかったのです。
このブログにも、たぶん以前この人物のことを書いた記憶があります。
もし気になる方は、よかったら探してみていただけますでしょうか。
心が疲れた時、途方に暮れた時、ここを訪れれば救われる気がするのでは
ないかと、そんな場所でした。いえ、場所だけではありません。
「ひと」も美しいのです。
日本に、いえこの世の中にこんな場所があるなんて。
そこはまるで別世界のようでした。
ふらりと立ち寄ったところで、思いがけずお話を聞くことができました。
お話を聞いて、涙が出ました。
こんな美しい話があるのかと。
思い出すと、また涙がにじみます。
「雪景色」。
そう、滋賀は雪が積もっていました。
雪解け水なのか、流れる水がとてもきれいなところでした。
せっかく写真を撮ってきたのですが、お見せできないのが残念です。
ミャクミャクも連れて行ったのですが、撮影スポットが見つかりませんでした。
帰りの電車で琵琶湖を見て、やっぱり海にしか見えないなと思いました。
帰りは新大阪で下車して、家族それぞれの駅弁を買いました。
お土産屋さんもチェックしたら、おお!黒ミャクのキーホルダー発見!
値段も見ずにレジに向かったのですが、思ったより高かったのでびっくり。
ミャクミャクビジネス、成功しましたね。
さあ、『ナレッジ・イネーブリング』もラストスパート。
今日こそ完走したいと思います。
それでは、みなさんもよい一日を!